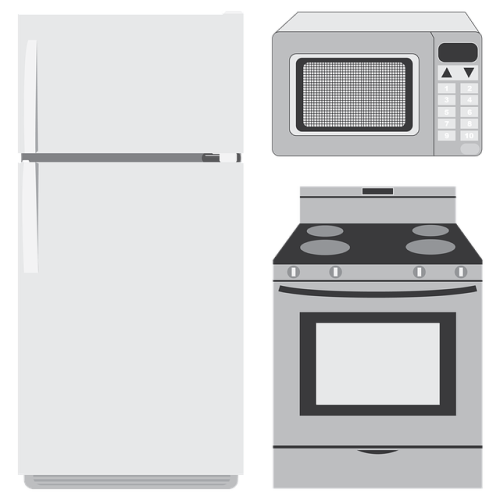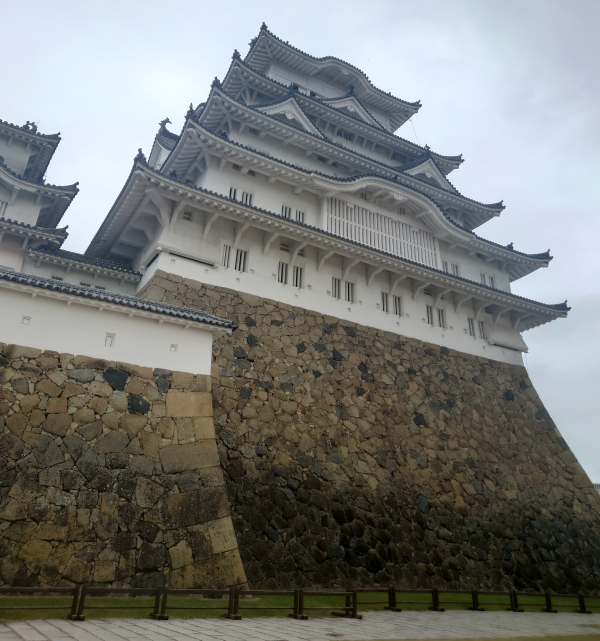結婚して今の家に住まいしてから、24年。
その時に新調した家電や住宅設備でいまだ活躍してくれている家電は
衣類乾燥機のみとなりました。
結婚して13、4年経った頃から、ガスコンロ、食洗機、トイレの温水洗浄便座、
エアコン、洗濯機、ガス給湯器、冷蔵庫など、
毎年何かが順調に?順番に調子悪くなっていきました。
使用頻度の高い住宅設備・家電や、水と電気を一緒に使用して稼働する設備は
故障しやすいのではないかと思います。
リビングのエアコンの取替(一度は基板修理を依頼)を最後に
我が家の家電、住宅設備の取り換え、買い替えは一通り終了しました。
次は一巡回ってガスコンロの取替かなと思っています。
エアコンなどは昔の物に比べてコンパクトでスリム化している分、
部品も小さく細くなっているせいか壊れやすくなっている気がします。
昔のエアコンが、ずっと壊れず使えているけど、
電気代が高くなるから取替えたという話もよく耳にします。
どの設備も毎日の生活の中で突然使用できなくなると困ってしまうものばかりですが
普段から使用後にお手入れをすることで故障のリスクが減り、
設備の寿命を延ばすことにつながります。
これから寒くなる時期、特に給湯器は負荷がかかり故障しやすい時期となります。
冬場にお湯が出ない・お風呂に入れないのは苦痛です。
お湯の出が悪い、温度が低いと感じられた際は、
早めの点検・修理・交換をされることをおすすめします。(E)